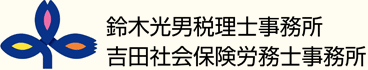労務管理
PERSONNEL LABOR
就業規則
Labor regulations
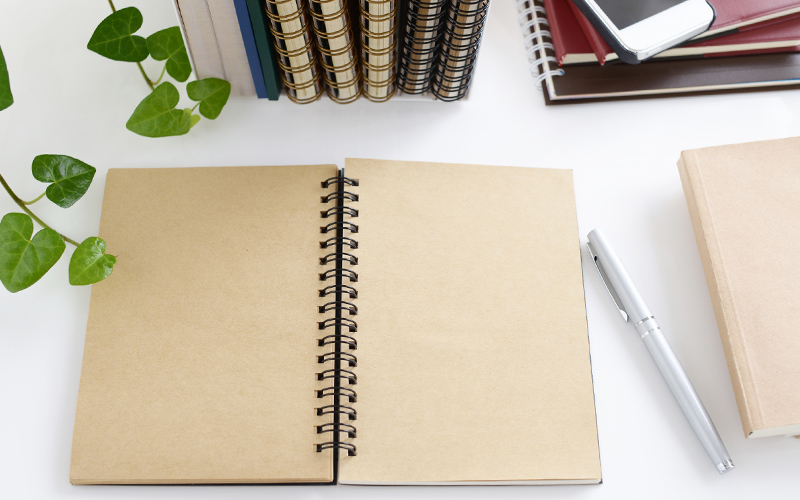
10人以上の労働者を使用する場合には就業規則の作成義務があります。しかし10人未満であっても、就業規則を作成することで、労使トラブルの防止や従業員の規律を正すことができます。
そしてなによりも真面目に働く従業員が損をしない仕組みを構築することが大切です。単なるルールブックではなく、会社の理念や求める人物像、評価基準などを盛り込んだ就業規則をご提案いたします。
当事務所が作成する就業規則の特徴
-
オリジナル性
会社の経営方針や現場の実態、または最新の労務トレンドを取り入れたオリジナル性の高い就業規則をご提案いたします。

-
リスク回避
今までに起こったトラブルや今後想定される紛争などを十分にヒアリングし、会社のリスク回避に貢献いたします。
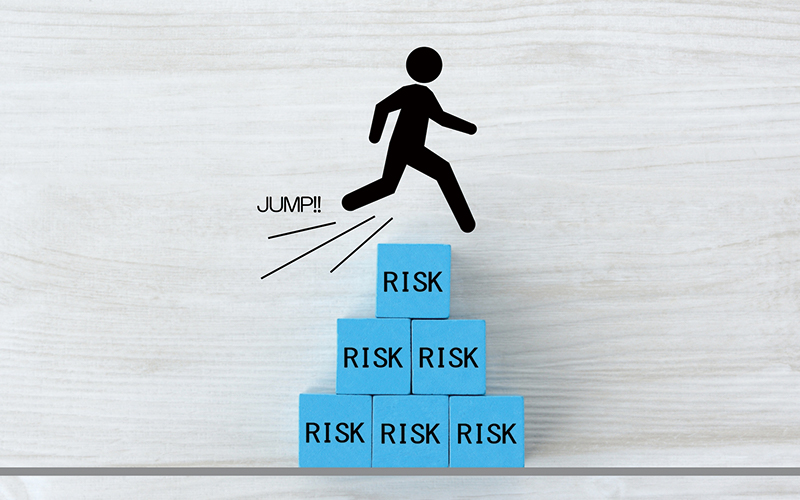
-
分かりやすさ
会社や従業員にとって読みやすく、会社の規模に応じたボリュームで作成いたします。就業規則は分厚ければ良いというものでもありません。

就業規則サポート
就業規則の作成・変更のみではなく、会社の希望に沿ったサポートをいたします。
-
諸規程の整備
退職金規程、車両管理規程、旅費規程等の作成

-
社内様式(ひな型)の提案
労働条件通知書兼雇用契約書、機密保持契約書、休職命令書等の作成

-
就業規則説明会の実施
全従業員、管理職、役員など対象者に応じた説明会の実施

就業規則が無い、または次のような就業規則をご使用の場合はご相談下さい
- 何年も前に作成し、その後変更した覚えがない
- インターネットや市販のひな型を使用している
- 社内で作成したが担当者の退職等により実態が分からない
- 法改正に対応しているか気になる
- リスク回避に重点を置きたい
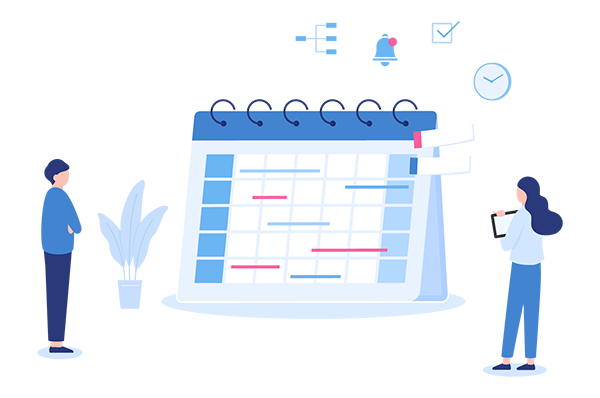
就業規則の無料診断受付中です
希望の場合は問い合わせフォームよりお申込み下さい。後日診断の流れをご案内させて頂きます。
-
就業規則診(簡易版・無料)
最大36項目から診断を行います。チェックリストをお送りいたしますので、ご自身で記入又は入力し当事務所までご返送下さい。後日診断結果をメールにてご案内いたします。

-
就業規則診断(簡易版・有料)
最大300項目から診断を行います。就業規則及び諸規程を当事務所にてお預かりいたします。概ね1週間程度で診断結果をメールにてご案内いたします。
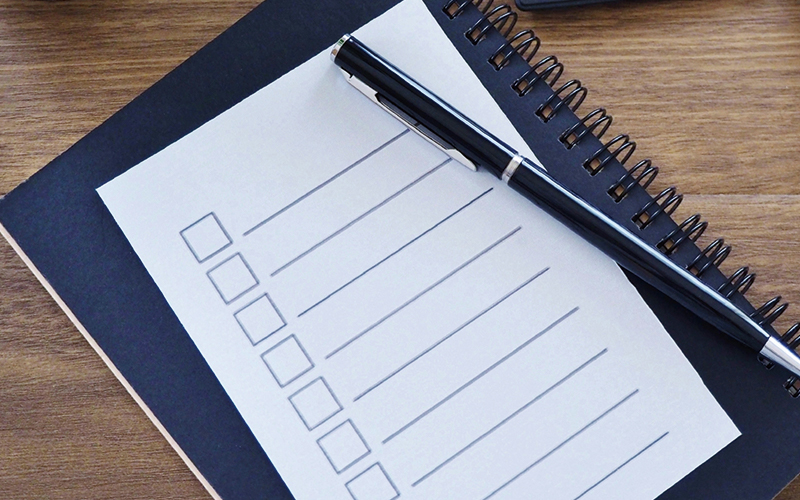
労務メモ
就業規則の周知
就業規則には周知義務があります。
労働基準法 第106条
使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。引用:労働基準法丨e-Gov
鍵のかかった書庫や、経営者しか立ち入ることができない場所などへの保管は周知義務を果たしているとは言えません。
必ず従業員が見やすい場所に掲示・備え付けを行う必要があります。
最近では社内の共有フォルダやグループウェアなど、電子媒体での周知も増えていますが、この方法でも問題ないです。
立派な就業規則を作成しても周知されていないと無効とされますのでご注意下さい。
就業規則と雇用契約書の優先順位
就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合はどちらが優先されますか?
労働契約法 第12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。引用:労働契約法丨e-Gov
就業規則と雇用契約書に異なる箇所があった場合は「従業員にとって有利な方」が優先されます。
人事制度
Personnel system
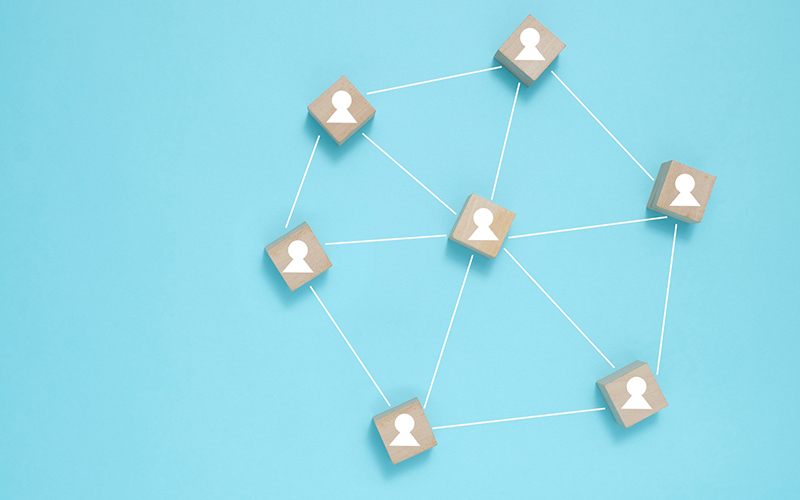
人事制度は簡単に言えば従業員の働き方に関する仕組みを整備することを指します。
例えば入社の際には労働条件通知書の交付または労働契約書を交わし、同時に誓約書、機密保持契約書、身元保証書など会社独自の手続きを行います。その他、賃金の決定や評価など様々な会社独自の制度があります。これらの制度の構築や実際の運用方法についてアドバイスさせて頂きます。
また従業員の配置や待遇が適正かどうか診断いたします。特に最近では過重労働や未払い残業代問題が深刻化しております。「その残業は必要か?」「変形労働時間制を導入できないか?」等の検討も必要です。
次のようなケースはご相談下さい
- 賃金体系を見直したい
- 評価制度を導入したい
- 残業が多くて困っている
- 雇用契約書や労使協定などチェックして欲しい
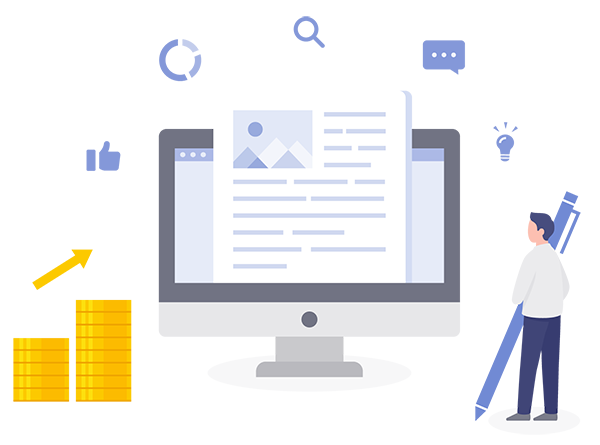
未払い残業代リスクの無料診断受付中です
希望の場合は問い合わせフォームよりお申込み下さい。後日診断の流れをご案内させて頂きます。
未払い残業代リスク診断とは・・・
管理監督者性、定額残業代、法定内残業、諸手当の4項目に着目して診断を行います。従業員数や労働時間から未払い残業代算出し、計算結果をPDFでご提案いたします。
労務メモ
労働条件の不利益変更
従業員の待遇を従業員の同意なく不利益に変更することは出来ません。
労働契約法 第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。引用:労働契約法丨e-Gov
ただし、次の場合は就業規則の変更によって労働条件を変更することが可能です。
労働契約法 第10条(抜粋)
①就業規則の変更が以下の事情などに照らして合理的であること
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
②労働者へ変更後の就業規則を周知させること引用:労働契約法丨e-Gov
就業規則の変更が合理的であれば認められるとの内容ですが、労働条件の不利益変更は従業員の生活に多大な影響を与えますので、従業員へ十分な説明を行い、個別に同意を取ることをお勧めいたします。
個別労働関係紛争の
未然防止
Preventing individual labor disputes

会社を経営する以上、従業員とのトラブルは避けて通れません。特に近年では労使関係は大きく様変わりし、紛争内容も複雑化を極めております。
しかしトラブルには必ず原因があり、殆どのケースでは労使のコミュニケーション不足が原因と言われております。
まずは当事者同士でよく話し合って頂き、それでも解決の糸口が見えないときはご相談下さい。関係が悪化してからですと解決が非常に困難となります。
お早めにご相談下さい
- 残業が増えてきて疲労感のある従業員が多い
- 会社の雰囲気が悪くなってきている気がする
- 最近退職者が増えてきた
すぐにご相談下さい
- 真面目だと思っていた従業員が問題社員化してきた
- 経営不振により整理解雇(リストラ)を検討している
- 労働基準監督署から指導が入った
※万が一労働審判や裁判に発展した場合は、提携弁護士をご紹介いたします。

労務メモ
問題社員
多く頂く相談内容が「問題社員」です。問題社員に対しては毅然とした対応をとることが大切ですが、これが出来ない会社が非常に多くあります。
「もう辞めてしまえ」「しばらく様子を見よう」は正しくはありません。指導の範囲を超えた発言や、見なかった事にするというのは事態を悪化するだけです。会社と問題社員の双方の視点に立って改善策を見つけ出す必要があります。具体的な方法は案件によって異なりますが、基本的には次の手順で進めます。
-
問題行動の明確化
問題行動の事実確認及び原因を探ります。
-
指導
軽微な場合は口頭で行いますが、内容によっては文書にて指導を行います。
-
改善の評価
問題行動が改善されたかを客観的に評価します。
改善されない場合は再度指導を行い、懲戒処分の検討に入ります。
整理解雇の4要件
会社の経営が悪化した場合に経営者が考える1つの方法として「整理解雇」があります。
通常の解雇と異なり、会社の事情による理由が大きいことから労働者保護が強まります。
従って以下の4つの要件を満たす必要があります。
-
人員削減の必要性
整理解雇をせざるを得ないほどの経営状態であること
-
解雇回避努力の履行
希望退職、配置転換、休業、役員報酬減額など、整理解雇を回避する努力を尽くしたこと
-
被解雇者選定の合理性
解雇対象者を選定する基準が合理的かつ公正であること
-
解雇手続きの妥当性
労働者に対して十分に協議、説明をしたこと
整理解雇は最終手段です。人員削減以外の方策が尽きた時に初めてに検討すべきものです。