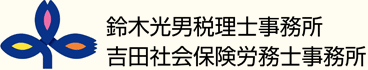手続き業務
PROCEDURE
労働保険・社会保険
Social insurance

入社から退職まで行政官庁に提出する手続きを代行いたします。手続は入社、退職だけではなく育休や定年再雇用、労災、私傷病休職・・・など様々あります。
定型業務ではありますが従業員個別の事情からイレギュラーなケースに発展することも良くあります。その都度手引きの確認や、行政への相談などを行っていてはそれだけで相当な労力になります。法改正にも対応する必要がありますので、それらの全てを専門家が引き受けます。
主な手続代行業務
- 従業員の入社・退社・異動に関する諸手続き
- 従業員の募集に関する手続き
- 労働災害、通勤災害が発生した時の労災申請
- 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の作成・提出
- 労使協定・意見書など労働基準法関連の書類作成・提出
- その他、労働保険・社会保険に係る諸手続き
次のようなケースはご相談下さい
- 手続きに時間をかける余裕がない
- 誤った手続きによって従業員からクレームがきた
- 行政官庁から調査の案内が届いた
- 手続き担当者が退職した、または退職しそうだ
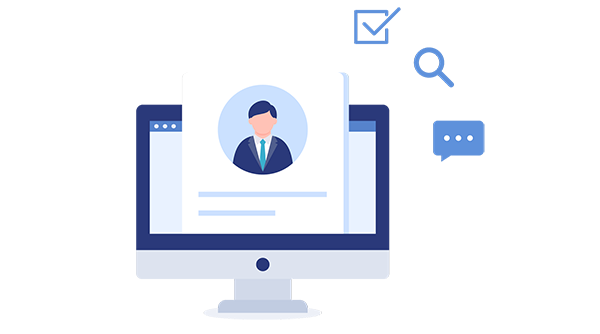
労務メモ
行政調査
行政の調査は次の通り分別されます。
労働基準監督署
-
定期監督
労働時間、残業代、最低賃金、有給取得等に違反がないかを調査します。定期的に行われ、対象企業の選定方法は業種を絞ったり無作為に抽出されるなど様々です。
-
災害時監督
労災が起こった際の原因及び安全対策、再発防止策の確認を行います。災害現場を直接確認します。
-
申告監督
労働者からの申告に基づく調査となります。労働条件や解雇など、労使トラブルから発展することが大半です。
-
再監督
違反を指摘されたにも関わらず是正報告をしなかった場合に行われます。
労働局
-
徴収室
労働保険料の申告が適正かどうかを調査します。毎年秋~冬にかけて行うことが多いです。
-
雇用環境・雇用均等室
女性の雇用状況や育児介護休業制度の活用状況について調査します。最近ではハラスメント対策に関する調査も増えております。
ハローワーク
助成金・給付金の申請が適正かどうかを調査します。申請に誤りがあった場合は助成金・給付金の返還を行う必要があります。
日本年金機構
社会保険への加入、標準報酬月額、賞与の手続きが適正かを調査します。社会保険の未適用事業所に対しても調査となる場合があります。
*大まかな分類となりますので上記以外にも調査はあります。
給与計算
Payroll processing

従業員を雇用したら無くてはならないのが給与計算です。毎月の給与計算は思った以上に負担になります。
社会保険料・雇用保険料の控除や料率変更のタイミング、年齢到達による社会保険料変更など、給与ソフトでは拾いきれない不規則な部分にも対応する必要があります。
業務の性格上属人化しやすく、また機密保持を求められますのでアウトソースするメリットは大きいです。
業務範囲
- 給与計算
- 賞与計算
- 勤怠集計
- 年次有給休暇の管理
- 賃金台帳、給与一覧表などの帳票の整備
- 年末調整(鈴木税務会計事務所)
次のようなケースはご相談下さい
- 従業員が増えて給与計算が面倒になった
- 残業代が正しく計算されているか不安だ
- 給与関係は従業員に任せたくない
- 勤怠システムを導入したい
※顧問契約の付帯契約となります。本業務のみの契約はできません。
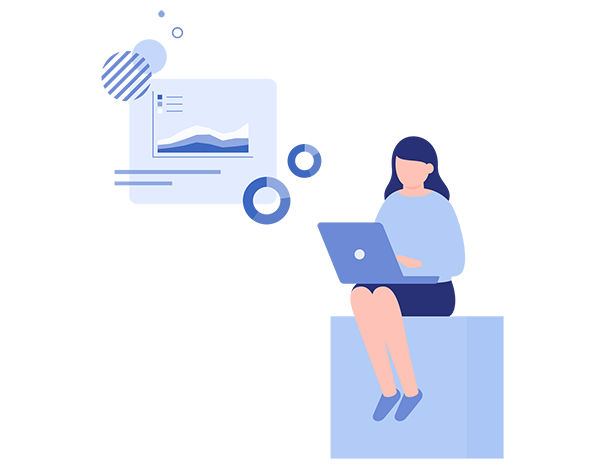
労務メモ
通勤手当
通勤手当は労使で自由に決定できますが、給与計算を行う上では次の考えに基づいて計算を行う必要があります。
-
労働保険・社会保険
全額賃金として労働保険料及び社会保険料の算定に含みます。
(ただし在宅勤務の場合は就業形態によって一部取扱いが異なります) -
源泉所得税
以下の表に定める金額を上限として非課税となります。
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 全額課税
特に自動車通勤の場合は自宅から会社までの距離によって変動しますのでご注意下さい。